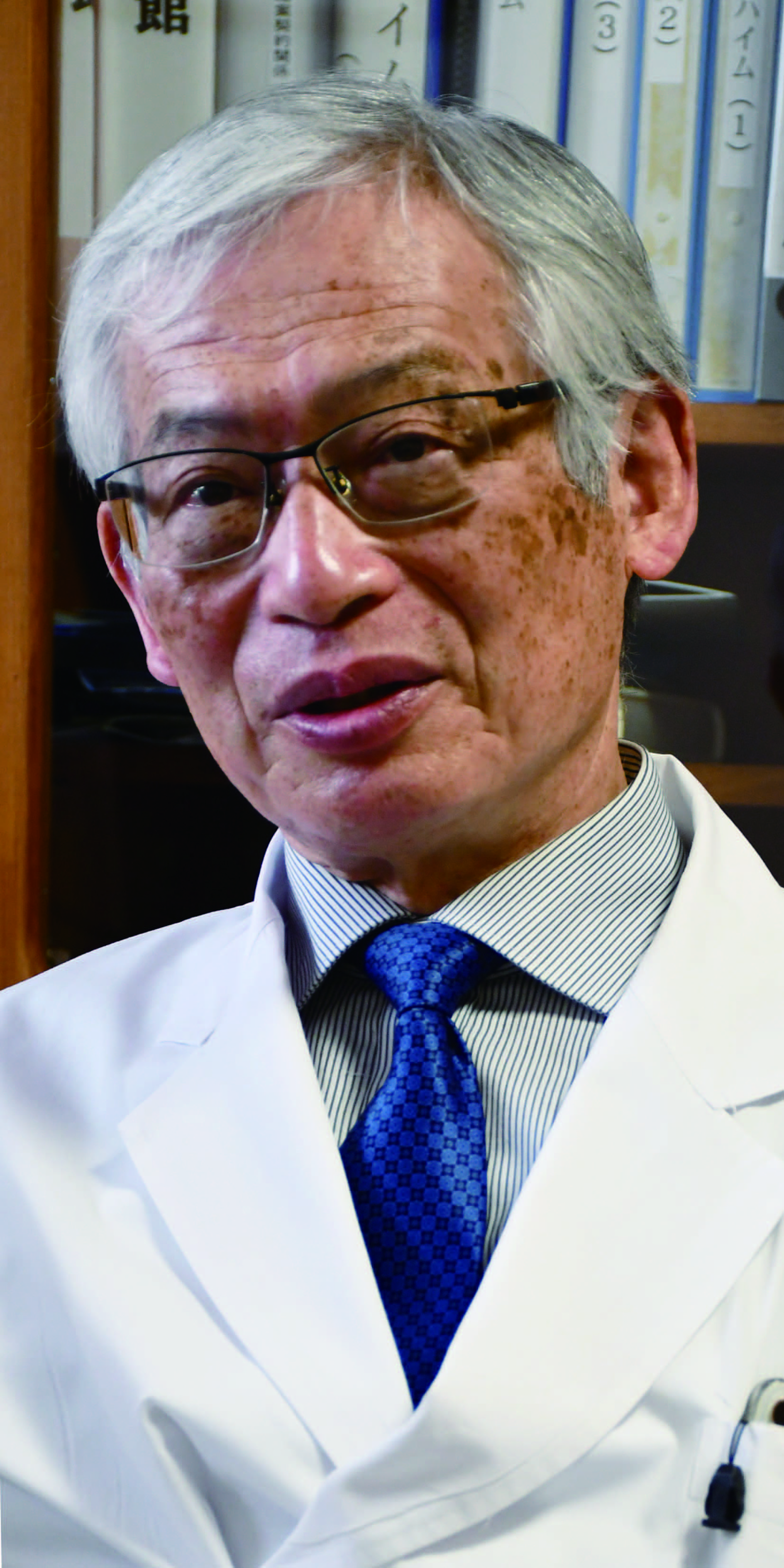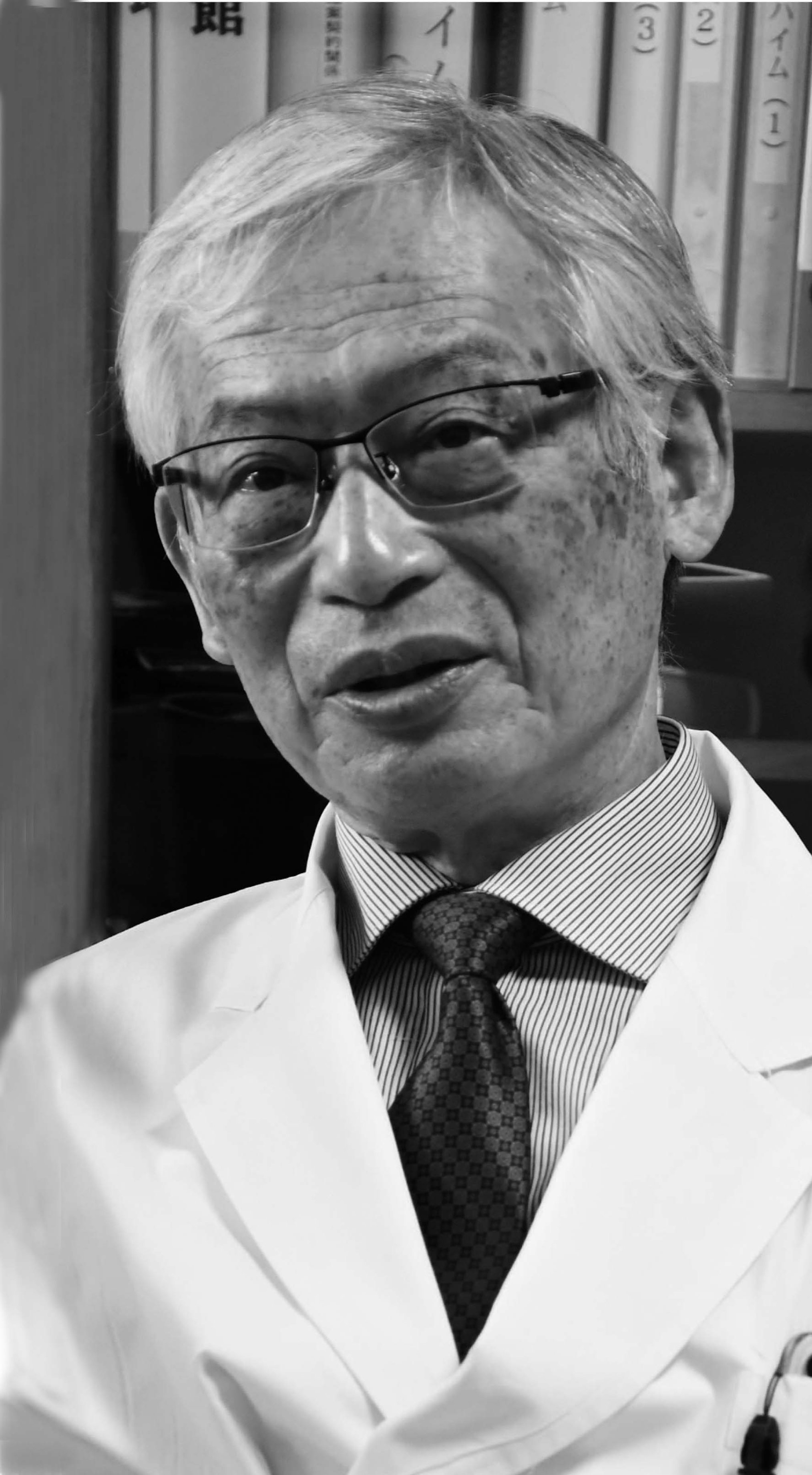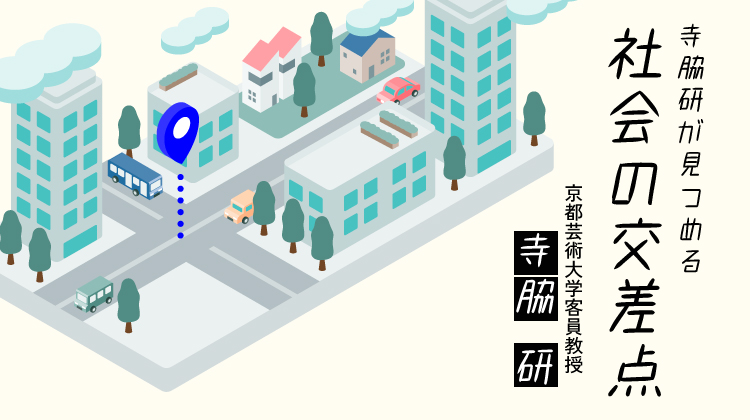内海 私は1949年1月に福島県で生まれました。これは父親の転勤によるもので、その後、たまたま愛知県に来まして、名古屋大学の医学部に進学。専攻したのが血液内科。そのまま大学に40歳くらいまで勤め、最後の3年間は附属病院第一内科の医局長という医局の取りまとめ役をしていました。
―― その後は、何ヵ所もの医療機関にかかわっていかれますね。
内海 ええ、「岐阜県立多治見病院に血液内科を作りたい」と病院側からの要請がありまして、行きたい人が誰もいないものですから、自分で行っちゃえと。そうして88年に多治見病院に血液内科を立ち上げ、部長として勤めていたのですが、93年に今度は医局の命令で国立名古屋病院(現・名古屋医療センター)に移れと。そうして赴任した先が、厚生省から東海ブロック(愛知・岐阜・三重・静岡)のエイズ診療拠点病院に指定されたのです。
―― HIVが混入した血液製剤が使われ続けたことなどもあり、日本でもHIV感染が拡大。その一方、エイズ患者への警戒や偏見も強く、診療体制整備が急務となった時期ですね。
内海 当時はエイズに対して「怖い」というイメージがわれわれ医療者の間でも非常に強くて、東京の大きな病院でも「エイズの患者さんは診ない」という方針を打ち出したりしていました。しかし、この地区でもどこかが治療に取り組まなきゃいけない。院長から「責任者をやりなさい」と言われ、当初はしぶしぶ引き受けたわけです。けれど、私にはHIV感染症、エイズに関する知識がまったくない。それで、ちょっとアメリカに行って勉強してこようと。
―― 40代後半での留学ですね。
内海 そうです。厚生省の留学制度を利用しようと申し込みをして、許可が出たのが95年3月。46歳でした。国としてはエイズ医療への推進政策をとっていたこともあって、留学することに関しては何の問題もなかったんです。ただ、お役所仕事には年度の区切りがあり、次年度への繰り越しはできないから、今月中に出発してもらわないと困ると言われ、米国での受け入れ先が決まっていない中での慌ただしい出発となりました。
アメリカ、そしてケニアへ
―― 留学先となったのはニューヨークのコロンビア大学。
内海 とりあえずサンフランシスコに行き、それから手当たり次第アタックするしかないと覚悟して渡米した私に、救いの手を差し伸べてくださったのが、NGOの人を介して紹介されたエイズ研究で高名な先生で、その方がコロンビア大学で学ぶプログラムまで組んでくださいました。
そうしてプログラムが始まり、アメリカでのエイズ治療の実態に触れると、普通に診療を行っていることに驚きました。しかもエイズ病棟はとても柔らかく穏やかな雰囲気に包まれている。もっと悲惨な状況を予想していましたから。
そうして5ヵ月間学んで帰国、翌年にも2ヵ月の留学をし、そうした治療を国立名古屋病院でもやろうと取り組んだところ、各部署も非常に協力的で、割といい体制づくりができまして、次の人にバトンタッチすることができたわけです。
―― それでもエイズとのかかわりは、その後も続けていかれますね。
内海 はじめは嫌々だったエイズ医療でしたが、医師としての軸足がそちらに移って行ってしまいまして、名古屋での予防活動に加え、ニューヨーク時代に知り合った医療従事者から「アフリカに行くぞ」と声が掛かったものですから、ついて行ってケニアのナイロビのスラム街でHIV感染検査なんかをやったり。
―― アフリカでのエイズ感染の悲惨な状況は日本でも報道されました。
内海 最初にアフリカに行ったのは2000年。そのときの陽性率は25%くらいで、特に30代の女性は50数%が陽性。本当にびっくりしましたが、国連から発表されているデータは嘘ではないと実感もしました。
しかし、実はその後、ニューヨークの先生とはケンカしてしまいまして、「別のところに行こう」と、ナイロビからずっと奥に入ったビクトリア湖のほとりにあるゲム村(ニャンザ州)などで予防活動を始めることになったのです。
―― その村とはどんな縁が。
内海 名古屋市在住の薬剤師さんでケニアが好きな人がいましてね、その方がわれわれのところを訪れ、「ケニアの親友の故郷でHIV感染症が蔓延している。何とかしてほしい」と。ちょうど某先生とケンカした後でしたから、その地で活動を始め、現在まで続いています。
―― 日本では昨今、HIVに対してあまり関心が持たれなくなっています。
内海 ええ、マスコミも取り上げませんし、感染者も減っているし、いい薬もでき、血液中のウイルス量を検出限界以下までに抑え込めばもう感染しません。ある意味、糖尿病よりコントロールしやすい病気になりましたから。
―― 医学の進歩は素晴らしいですね。しかしケニアなどではまだそうなっていないのでしょうか。
内海 発生率は下がっています、ケニアでも政府が抗HIV薬を無料で供給できるようになりまして、ゲム村でも当初は23%が陽性でしたが、2019年には新たに検査した人の陽性率が1・6%まで下がりましたので、われわれの目標は達成されたと思っています。
ただ、向こうで問題の病気はHIV感染症だけではありません。いろんな感染症、いろんな病気があるけれど、貧しいので医療機関にかかれないのです。だから貧しい人たちにも医療を提供できるようにしようと、現地のNGOと合同で診療所を建て、現地の医療人材も育てています。
人としての豊かさとは
―― アフリカではさまざまな経験をされたことでしょう。
内海 アフリカはね、皆が貧しい。お金を持っていないから診療所にもかかれないくらいです。だけど、われわれの無料診療の時には来るわけで、20歳前後のある女性は「突然意識がなくなって倒れてしまう」と言うので、「癲癇(てんかん)だね。どこか治療に通っているの?」と聞くと、「お金がなくてとても通えません」と言う。保険に入っているわけもなく、生活保護とかの制度もない。本当に何の保障もない〝丸裸〟で彼らは生きているんです。
ある時、「重症患者がいるから往診してくれ」と言われましてね、行ったんですよ。すると、掘っ立て小屋のベッドに女の人が横たわっていて、起き上がることもできない。そして、その横には赤ちゃんがいる。「ああ、この親子は死んでしまうんだな…」と思いました。だけど、そんな彼女を貧しい中でも〝誰か〟がケアしているんですよ。誰かが玄関の先に座って彼女を看ている。何もできないけれど、それでも誰かが寄り添っている。家族でも何でもない人たちが、必ずついているんです。それには感動しましたね。
―― せめてできること、「そばにいてあげる」ということをしていると。
内海 そう。一人きりじゃない、誰かがいるということは、心強いことですよね。
ケニアのスラムとか田舎に比べれば、日本はどこであっても物質的には豊かでしょう。だけど、人を助けるとか、未来への希望があるとか、皆で支え合って生きるとか、そういう精神的なことでは、どちらが本当に豊かかわからないですねえ。
私の周囲に人生につまずいた人、例えば離婚をして、奥さんだけでなく子供とも別れてしまい、「もう何の生きがいもない…」と無気力になった男性がいました。「一緒においで」とアフリカの活動に連れていったら、帰国後、気持ちを入れ替えて働くようになりました。また、「自分はこのままでいいんだろうか」と悩んでいた看護師に「一緒に行こう」と連れていったら、立ち直って看護学校の先生をやり出しました。
甘えることなく頑張って生きているアフリカの人たちの姿を見て、「自分も頑張って生きよう」と思えるようになるんじゃないでしょうか。そういう力を、私たちは与えてもらえているんです。
―― 渡航費用などは参加者負担で?
内海 そうです。20数万円の旅費は自分で払ってもらい、10日ほど休みを作って行くのですが、一度参加した人は、何度でも行きたがります。チャーターするバスの都合で毎回20人ほどが限度なのですが、みんなが行きたがる。もちろん私も行きたい。そうした不思議な魅力がアフリカにはあり、学ぶことも本当に多いです。
「嫌だ」と思う道をあえて選択
―― なかなか変化に富む経験を積まれていますね。90年代前半にエイズ治療の最前線に身を置く立場にいなかったら、また違った医師人生を送られたことでしょう。
内海 そうでしょうね。しかし、人生、何がいいかわからない。むしろ「嫌だな」と思う方へ進んだ方が、人生経験が豊かなものになるだろうと思います。医局長をやれと言われた時も「めんどくさい仕事だな」と思いましたし、高山の病院から「来てくれ」と言われたときは本当に嫌でしたが。
―― 岐阜県厚生連高山病院ですね。
内海 もとは国立病院機構の高山病院という結核療養所だったところです。結核患者も少なくなって多額の赤字を抱え、国立病院機構としては廃止しようとしましたが、地元の人々が存続を求め、厚生連に移譲しようということに。でも厚生連の各病院長は、ただでさえ病院経営は大変なのに、そんな赤字の病院を自分たちで抱えるなんて、と大反対をしていたんですよ。
その急先鋒が私の先輩で、厚生労働省から私のところへ電話がかかってきて、「あの院長を説得してくれ」と言う。「なんで自分がそんなことを」と言ったら、「知り合いだろうと」。良く調べたもんですねえ。その後さまざまなやり取りがあり、先輩にいろいろお願いして、厚生連への移譲が実現できたんです。
―― 2003年から先生がそこの院長を務めることになったのは、
内海 私の先輩がその病院の院長も兼任することになったのですが、ある時「内海君、相談がある」という電話がありました。私、高山が好きなものですから、「じゃあ遊びに行きます」と出掛けたところ、「内海君、どちらかの院長をやってくれないか」という話でした。そんな展開になるとはこれっぽっちも思っておらず、「なんで私が」という思いがありましたし、言われた瞬間に吐き気も。肉体が拒否していましたね。
ただ、その先生はものすごく働く先生だったんです。朝7時には病院に出勤して夜の11時ごろまで働き、正月は自ら当直をし――という人からの要請です。これを断ったら絶対後悔するとも思いました。1ヵ月くらい悩みましたけど、ケニアからの帰国でアムステルダムから乗った飛行機の中、「よし、行こう」と決意し、翌年、高山の病院に赴任しました。
高山病院での改革
―― 赤字を抱える病院のけん引役。存続のためには経営改革も必須ですね。
内海 ものすごい赤字を出していたんですよ。年間の医療収入額の40%くらいに相当するとんでもない赤字額。なにしろ外来患者さんだけでなく入院患者さんも少なく、ベッドの利用率は7割を切っていて、それなのに救急患者の連絡が来ても「別の病院に行ってくれ」と断っている。「何やっているんだろう」という状況でした。
―― しかし地域の人々が存続を強く願ったくらいですから、医療機関としての需要はあるはずでは?
内海 そうです。だけど、そこで働いている人たちは、給料は国立だから必ず確保されるわけで、できるだけ楽をして給料をもらおうとしているように私には見えました。
だから、私が院長として最初に挨拶したときも、皆横を向いていて、「何しに来たんだ」「これまでの体制を乱す気か」という雰囲気が感じられましたが、そのままではいけない。赤字ということは、どこかから補填されるわけですからね。
それは他人の労働の成果を持ってくるということ、人の労働の成果を当てにしているということです。「それは大人としてずるいぞ。自分たちでできるだけのことはやろうじゃないか」と申し上げた。
もう一つ、医療というのは、お金に換えられない喜びがある職種だと思うんです。患者さんが良くなって退院していくこと自体に喜びややりがいを感じられる仕事です。「嫌々やるんじゃなくて、そういうのを求めていこうじゃないか」と。
多くの職員が徐々に変わり、協力的になっていきました。まあ、最後までその路線に乗ってこない人たちも残念ですけど一部にはいましたが、私が在籍した4年半で、ほんのちょっとですが黒字を出せるようにまでなりました。
―― その高山から08年に名古屋に戻ってこられます。
内海 国立名古屋医療センターの院長から「戻ってこい」と。まあ、何とか黒字を出せるようになったので、戻ることを決めたんですけど、バトンを引き継いでくれる人がいなくて、本当に探し回りました。だけどある先輩が、「行ってもいいよ」と言ってくださった。ありがたかったなあ。
「どうしてOKしてくれたんですか」と聞いたら、僕が医局長をしていたとき、その先生が困って「医師を派遣してくれ」という求めに応じたことがあったそうです。こちらは覚えていなかったのですが、その先生は恩を感じてくれていたらしいです。
―― 人の縁が大切なんですね。
内海 国立名古屋医療センターで副院長を務めた後、10年から行った国立病院機構東名古屋病院も「嫌だな」と思いながらの就任でしたが、大変勉強になりました。そして15年からは愛知県の地域医療支援センター長になり、そこでは高山で地域医療を勉強したことが役立ちました。
そして21年、これも先輩だった聖霊会理事長から「内海君、あとをやってくれ」ということで、県の方を辞めてこっちに来たというわけです。財政事情を見たら、これまたびっくり。莫大な借金を抱えていて、非常に経営が難しいです。それでも少しずつ前進はしています。私も理事長ですと普通、現場に出ず指揮を執っていればいいものですが、そんなことも言っていられず、月に12回くらい外来診療に出ています。
「死」と向き合って
―― 先生は終末期医療にもかかわってこられました。
内海 血液病の診療をやっていると非常に重症な方が少なくありません。特に白血病とかは、よくなる人もいますけど、若くして死を迎える人もいるわけで、医師として「死」というものに、遭遇することは多かったと思います。
そうして多くの患者さんを診てきましたが、ひとり、とんでもない人がいました。40代後半の女性でしたが、〝死〟を完全に受容していたんです。白血病を告知しますが、ぜんぜん動じない。完全に受け入れていて、いったんよくなったものの再発した時、骨髄移植を勧めたのですが、「私は十分生きましたから、いいです」と断られた。それは嘘偽りない言葉でした。
私が受け持った患者さんの中には、なかなか死を受容できない人もいるわけです。中にはつらい治療の中でパニック状態になって壁に頭を打ち付けたり、ナースコールを押し続けたり、医療者だけでなく家族にも攻撃的になったり…。でも前述の女性に会わせると、皆、死を受容するようになる。哲学者でも宗教家でもカウンセラーでもない、普通の平凡な主婦の方でしたが、すごい人でした。
―― 死は誰にも必ず訪れるものですが、〝自分事〟となると、普通はなかなか受け入れがたいものなのかもしれません。
内海 ええ。私も医療従事者として「死」というものに関してちょっとは勉強したりしたんですが、でもそれは患者さんの死、他者の死で、いってみれば対象化された死です。70歳になった時、父親が60代で死んでいたこともあって「いよいよ自分にももうじき死がやってくる」と思ったら、死というものに押しつぶされそうになりました。
何とかしようと、いろんな本を片っ端から読んだのですが、どれもピンとこない。でも、ある一冊の本が少しだけ私を救ってくれました。それはフランスのある進化論者、古生物学者、地質学者が書いた進化の本でした。 46億年前に地球ができて、当初は単純な原子、分子の世界だったのが、高分子ができ、細胞ができ…という複雑化の過程を経て生命が誕生し、生命から精神が誕生した。では今後の進化がどこで起こるのか。それは精神の進化だろう、〝聖なるもの〟に向かうだろうと、その著者は言うわけです。
確かにそうでしょう。いままでの進化の歴史をみれば、これからは精神の進化。だったら、そういったもの、〝聖なるもの〟にほんの100万分の1㍉㍍でもいいから近づけるよう、コントリビューションできれば、それで自分の人生はいいんじゃないか、と。死によってすべてが消え去るわけですけれど、でもその足跡がどこかに、ほんのちょっとだけでもあればいいのかなと思えるようになりました。
そういうことを、私は医師としての活動の中で学びました。
―― ありがとうございました。