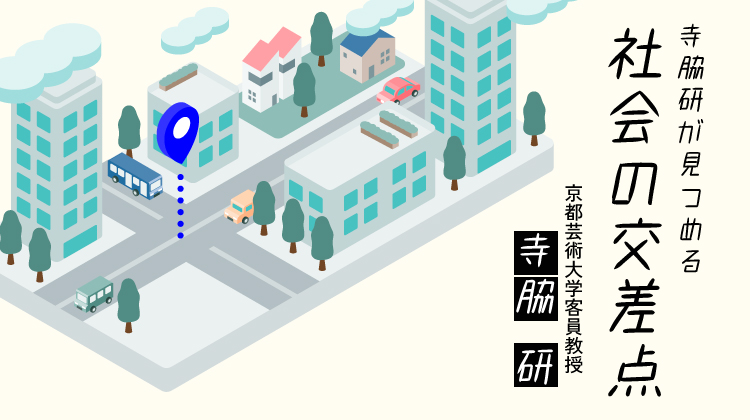外交では「台湾有事」は日本の「存立危機事態」になると踏み込んだ発言を行い、中国と緊張が高まっている。それに対して内政面になると、とたんに歯切れが悪くなる。
今年5月には物価対策として食料品にかかる消費税率8%をゼロにすると主張していたが、総理になると自民党内の意見が割れているという理由でうやむやになり、かつ最低賃金1500円目標も取り下げられ、電気・ガス料金の引き下げやお米券配布でお茶を濁そうとしている。
国家が「例外状態」あるいは「極限状態」になると、国のトップはどの国が敵であるかを決断しなければならないが、中国とそうした状況に今はない。一方、国民の生活水準は四半世紀も低下し続け、過半の人は食料品高騰で「極限状態」に近づきつつある。
国民の生活水準を最も表している指標は実質賃金であり、1996年をピークに2025年9月時点で16・2%減(年率0・6%減)となっている。この29年間の間に実質賃金が上昇したのはわずか6年にすぎず、23年間も下落。景気が回復しても賃金は上がらなくなっている(図参照)。
景気対策あるいは経済成長戦略は結果的には株価対策となっており、日本はもはや自由主義国家とはいえなくなりつつある。貨幣経済において自由は所有の関数となっていて、実質賃金が増えなければ、所有(金融資産)は増えないからである。
E:「テクノロジー教」に 取りつかれた日本]
「現在のわれわれは、テクノロジーとそれがもたらす進歩に取りつかれている」(アセモグル&ジョンソン『技術革新と不平等の1000年史』)。テクノロジーやイノベーションは確かにそれ自体技術の「進歩」であり、経済成長を促す。しかし、ドラッカーが言うように、「経済の成長と拡大は、社会的な目的を達成するための手段としてしか意味がない」のであって、「経済的な進歩が個人の自由と平等を促進するという信念」に基づいている必要がある(『「経済人」の終わり』1939年刊)のだが、この信念は四半世紀にわたって消滅している。
技術進歩による経済成長は労働生産性の上昇をもたらす。それに見合って実質賃金は上昇するのが経済原則である。しかし、1996年以降も労働生産性は年0・6%で伸びているにもかかわらず、実質賃金は年0・6%減となっている。賃金が減少しても前年の生活水準を維持しようとすれば、金融資産を取り崩すことになる。これが長年続いたため、金融資産を保有しないと答える世帯は24%に上る(1987年は3・3%)。国民からみれば「例外状態」であるから、この事態を収拾するために決断しなけばならないが、高市総理は与党議員すら説得できない。
日本政府は小泉政権の「骨太の方針」以来、テクノロジー教(技術進歩教)の信者となり、その信仰はアベノミクス、そしてサナエノミクスへと受け継がれている。2001年に誕生した小泉政権以降、政府の経済政策の基本路線は供給サイド重視で企業優遇であり、家計への配慮は後回しとなっている。企業の自己資本利益率(ROE=当期純利益/自己資本)は小泉政権誕生時の01年度マイナス0・1%から24年度9・6%と、バブル絶頂期の1998年度9・9%以来の高い水準となった。
[E:過剰な資本と過剰な利益という現状をどう是正するか]
「明日のことなど少しも気にかけないような人こそ、徳と健全な英知の道を最も確実に歩む人」であると、ケインズは称賛している(『わが孫たちの経済的可能性』1931年刊)。
経済成長が自由と平等を促進すれば、ケインズのいう社会に近づくことができることになる。そのために、ケインズは「貪欲は悪徳であるとか、高利の強要は不品行であり、貨幣愛は忌み嫌うべきものである」という。
ところが、現実には24年時点で「貨幣愛」を追求してやまないビリオネア(10億ドル長者)2769人が純資産額15・3兆㌦(1人当たり55億㌦)を保有し、1987年の140人、純資産2950億㌦(1人当たり21億㌦)から急増している。
本来、資本が利潤を生むのは、その希少性にある。しかし、毎日10㌧トラック約1270台に相当する食品ロス、年10億点にも及ぶとされる新品の衣料品の大量廃棄、900万戸の空き家など資本は過剰にあり、その過剰な資本を稼働させるために長時間労働を強いられている。資本が過剰であれば、ROEが下がるはずであるが、逆に上昇している。またケインズは実質金利がマイナスになると、資本の利潤率は土地利回りより低くていいという。土地の希少性はなくならないからである。
東証RIET指数の分配金利回りは4%半ばで推移しているため、ROEは4%前後が適正値となる。24年度の当期純利益は40兆円程度で十分である。実際の利益額89・6兆円のうち50兆円が人件費と銀行への利払い費にあてることが可能となる。労働者と預金者への分配を25兆円ずつとすれば12・5%賃上げが可能となり、個人預金には2・5%の利息がつく。「強い家計」への第一歩となるだろう。